
「S&Cコーチとしての考え方」の記事一覧

#886 アスリートから「競技中の〇〇動作を改善したい」と相談された場合の対応策

#885 競技中の〇〇動作を改善したいからといって、〇〇動作に外的な負荷をかけた筋トレエクササイズをやっても課題解決には繋がりません

#882 情報をインプットするときは批判的思考(クリティカル・シンキング)が大切

#874 スポーツ現場における「インビジブルモニタリング」とは?

#871 アスリートの「感覚」と「実際の動き」をすり合わせておくと調子が崩れたときに役に立つ

#870 アスリートの「感覚(=input)」と「実際の動き(=output)」は違う場合がある

#865 【アスリート・競技コーチ向け】「ちょっと〇〇を痛めているので、筋トレは休んで練習だけ参加します」というのがダメな理由

#864 特定の筋肉を「アクセル筋」とか「ブレーキ筋」と呼ぶのはナンセンスです

#863 体重をできるだけ増やしたくないスポーツ競技の分類

#862 バスケの「インテンシティ」をS&Cコーチがトレーニングで高めることは可能か?
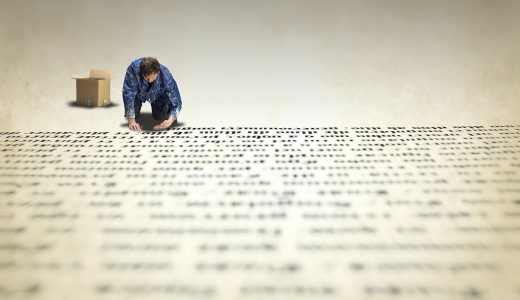
#858 トレーニング指導において「マニュアル」は善か悪か?

#855 アスリートがトレーニングをやる意味を上手に説明している記事を見つけたので紹介します:焼き芋屋さんとカレー屋さん

#852 フィットネスと疲労を数値化するのは難しいけど、それでも「フィットネスー疲労理論」を理解しておくべき理由

#851 トレーニング指導を受けるなら週1回より週2回

#847 ウエイトトレーニングによる「ケガをしづらい身体づくり効果」がアスリートに理解してもらいづらい理由

#845 科学的知見に基づいたトレーニングが確率論で考えると最善である

#843 結論の一貫性ではなく思考過程の一貫性を重視し、言うことが変わることを恐れない

#841 ウエイトトレーニングをすると「痛みが出にくくなる」というメリットを短期間でも実感しやすい
